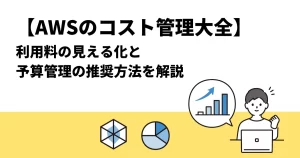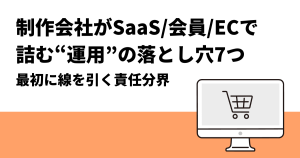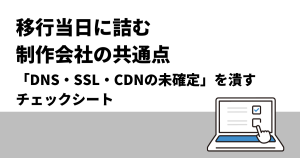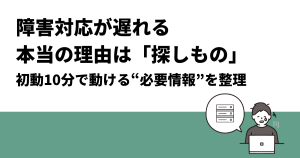Web制作会社では、クライアントから受託されたサイトの運用・保守において、多くの課題に直面するケースが増えています。本記事では、下記のように課題を外注することによってどのように解決できるかを具体的に解説します。
Before(現状の課題)
- サーバー容量の逼迫による突発的なトラブル
- SSL証明書やセキュリティ要件への対応責任が曖昧
- 夜間・休日のアラート対応による担当者の負荷増大
- クライアント要件を満たす具体的な方法が不透明
After(外注による解決)
- 監視・容量管理・SSL更新の自動化により安定運用を実現
- 責任分担の明確化でクライアント説明が容易に
- 夜間対応の外注化により社内リソースの最適配分
- 要件遵守の具体的手法が明確化
この記事でわかること
① よくある4つのサーバー運用課題
② ディレクター/PMの業務負荷軽減イメージ
③ サーバー保守会社に外注可能な業務範囲
当てはまる課題のチェック(4項目)
以下の項目に該当する場合、現在の運用体制に改善の余地があると考えられます。
小容量(〜40GBほど)で使用率7割前後
典型的な状況
- WordPressサイトで容量30〜40GB、使用率が70%前後に到達
- アップロード画像やログファイルの蓄積により容量が徐々に圧迫
- 使用率80%を超えると動作が不安定になるリスクが高まる
潜在的なリスク
容量不足によるサイトダウンは、クライアントのビジネスに直接影響を与えるため、Web制作会社としての信頼性に関わる重要な問題となります。
ピーク時にリソース逼迫の兆候
具体的な症状
- アクセス集中時(キャンペーン時など)に表示速度が著しく低下
- CPU使用率が90%以上に達する状況が頻発
- メモリ不足により503エラーが断続的に発生
影響範囲
リソース逼迫は、サイトの表示速度だけでなく、SEOやユーザーエクスペリエンスにも悪影響を及ぼす可能性があり、クライアントのビジネス成果を阻害する要因となります。
SSL/ドメイン/DNS管理の対応責任が曖昧
よくある問題
- SSL証明書の更新タイミングや担当者が不明確
- ドメイン管理がクライアント側かWeb制作会社側か曖昧
- DNS設定変更の権限と責任範囲が整理されていない
リスクの深刻度
SSL証明書の失効は、サイトへのアクセス阻害やセキュリティ警告表示に直結し、クライアントのブランドイメージに重大な損害を与える可能性があります。
クライアント要件の遵守方法が不透明
典型的な課題
- 「24時間監視」や「99.9%の稼働率」などの要件に対する具体的な実現方法が不明
- バックアップ頻度やデータ保持期間の要件を満たす手法が確立されていない
- セキュリティ基準への準拠を証明する仕組みが整備されていない
この状況では、クライアントへの説明に苦慮し、案件の信頼性確保が困難になります。
外注するとディレクター/PMの負荷はこう変わる
運用・保守を外注することで、ディレクターやPMの業務負荷は以下のように変化します。
| 項目 | Before(現状) | After(外注後) |
|---|---|---|
| 監視・アラート | 属人的な対応/ルール不明確/夜間・休日の緊急呼び出し | 監視閾値・通知・エスカレーションルールを事前定義、 夜間対応を外注化により担当者の負荷軽減 |
| 権限管理 | 管理者権限の所在が不明確/アクセス情報が社内に散在 | 外部には必要最小限の権限のみ開示、 管理は外注先で集中化、依頼窓口を明確化 |
| セキュリティ | SSL証明書更新が属人的/失効リスクが常に存在 | 証明書更新の自動化と恒常的な監視により失効リスクを排除 |
| 要件対応 | クライアント要件を満たせるか不透明/社内説明に苦慮 | 外注範囲と社内分担を明文化し、 要件遵守の具体的手法を確立 |
ディレクター/PMが注力できる業務
- 新規案件の企画・提案活動
- クライアントとの要件調整・コミュニケーション
- プロジェクト全体の進行管理と品質向上
実際の案件でよくある課題とその解決例
実際の運用現場で発生する代表的な課題と、外注による解決アプローチをご紹介します。
容量逼迫 → 容量拡張/ログ圧縮で安定化
ケース例
コーポレートサイト(WordPress)で、月次の商品紹介記事とイベント写真の蓄積により、6ヶ月間で使用容量が20GBから38GBに増加。使用率75%に達し、管理画面の動作が重くなる症状が発生。
解決アプローチ
- 即座に容量を50GBに拡張し安定稼働を確保
- 画像最適化により既存データを約30%圧縮
- アクセスログの自動ローテーション(30日保持)を設定
- 月次で容量使用状況をレポート、必要に応じた事前拡張を実施
期待できる成果
使用率を50%台に維持し、安定した表示速度を実現。クライアントからの「サイトが重い」という指摘を解消。
権限曖昧 → 管理区分を整理し依頼窓口を明確化
ケース例
ECサイトの運用で、制作会社・システム開発会社・クライアント担当者がそれぞれサーバー権限を保有。SSL証明書更新時に権限競合が発生し、サイトが一時アクセス不可に。
解決アプローチ
- サーバー管理権限を外注先に一元化
- 制作会社には必要な作業依頼権限のみを付与
- 緊急時のエスカレーションルールを文書化
期待できる成果
権限管理の透明性が向上し、SSL更新等の定型作業でのトラブルが皆無に。クライアントへの説明も論理的かつ明確に行えるようになります。
SSL更新不安 → 恒常管理で失効リスクを防止
ケース例
複数ドメインを運用するメディアサイトで、SSL証明書の更新タイミングがバラバラ。担当者の見落としにより、1つのサブドメインで証明書が失効し、「安全でない」警告が表示される事態が発生。
解決アプローチ
- 全ドメインのSSL証明書を統合管理システムで監視
- 更新日が近づくと日数の段階に応じたアラート設定
- Let's Encryptによる自動更新とワイルドカード証明書の活用
期待できる成果
SSL証明書の失効リスクが完全に解消され、クライアントからの信頼性が大幅に向上。制作会社としてのブランド価値向上にも貢献できます。
外注で任せられる運用・保守の範囲
外注により対応可能な運用・保守業務の具体的範囲を例としてご説明します。
監視と容量管理(閾値・通知・バックアップ/ログローテ)
24時間監視体制
- サーバーリソース(CPU・メモリ・ディスク)の常時監視
- Webサイト応答監視(レスポンスタイム・ステータスコード)
- データベース接続・パフォーマンス監視
自動化による安定運用
- 容量使用率80%でアラート、90%でスケールする設計
- ログファイルの自動ローテーション(アクセスログ30日、エラーログ60日保持)
- 日次バックアップとリストア可能性の定期検証
恒常的な監視とレポーティング
- システム稼働率・パフォーマンス指標などの監視。インシデント概要と対策の報告
- 容量計画・パフォーマンス最適化の改善提案
権限・アクセス制御(最小権限、MFA導入)
セキュリティ強化施策
- 最小権限の原則に基づくアクセス制御設計
- 多要素認証(MFA)の全管理者アカウントへの導入
- 不要なポート・サービスの無効化
アクセス管理の透明化
- 管理者アクセスの全件ログ記録
- 定期的なアクセス権限レビュー
- 退職者・担当変更時の権限削除
責任分担の明確化
1. 完成図書や運用計画書はWeb制作会社に共有
- サーバー構成図・ネットワーク図の提供
- 運用手順書(バックアップ・リストア・緊急時対応)の作成・共有
- 定期メンテナンス計画の事前通知
2. SSL証明書などの管理
- SSL証明書の取得・更新・管理を一元化
- ドメイン・DNS設定の変更管理
- セキュリティパッチ適用の計画・実行
Web制作会社側で継続する業務
- クライアントとの要件調整・コミュニケーション
- コンテンツ更新・機能追加の要件定義
- デザイン・ユーザーエクスペリエンスの改善提案
この責任分担により、制作会社はクリエイティブな業務に専念でき、技術的な運用リスクは専門業者が担うという最適な役割分担が実現できます。
よくある質問
外注ベンダーに任せられる作業と責任範囲は?
技術的作業範囲
- サーバー・インフラ環境の構築・設定・維持管理
- セキュリティ対策の実装・運用(ファイアウォール、SSL、アンチウィルス等)
- パフォーマンス最適化・チューニング
- 障害発生時の一次対応・原因調査・復旧作業
責任範囲
- サービスレベル合意書(SLA)に基づく稼働率保証
- セキュリティインシデント発生時の迅速な対応・報告
- バックアップデータの保全・リストア作業
- 技術的な改善提案・予防保全
責任範囲外(制作会社側で管理)
- クライアントとの契約・要件に関する最終決定
- コンテンツ・デザインの品質に関する事項
- ビジネス要件の変更に伴うシステム改修
クライアント要件の整理はどこまで支援してもらえる?
要件整理支援の内容
- クライアントが提示する運用要件の技術的実現可能性の評価
- 曖昧な要件(「高いセキュリティ」「安定した運用」等)の具体化支援
- 要件を満たすための技術的手法・コストの提案
具体的な支援例
- 「99.9%の稼働率」→ 監視・冗長化・保守体制の具体的設計
- 「強固なセキュリティ」→ SSL・ファイアウォール・アクセス制御などの詳細仕様
- 「迅速な障害対応」→ ・エスカレーション手順の文書化
クライアント説明資料の提供
- 技術的要件を非技術者にも理解できる形で文書化
- 費用対効果を含めた提案書の作成支援
- 定期的な運用報告書のフォーマット・内容の標準化
この支援により、Web制作会社はクライアントに対して強みに注力した提案ができるようになり、案件の受注確度と満足度の向上が期待できるのではないでしょうか。
本記事でご紹介したようにWeb制作会社様が抱えるサーバー運用課題は、外注によって大きく改善できる可能性があります。クロジカサーバー管理では、こうした運用課題を共に解決していただけるパートナー企業様との協業体制を整えています。
報酬制度やサポート体制を含め、安心して長期的に取り組める仕組みをご用意しております。
詳細は下記ページよりご確認ください。
監修者:クロジカサーバー管理編集部
コーポレートサイト向けクラウドサーバーの構築・運用保守を行うサービス「クロジカサーバー管理」を提供。上場企業や大学、地方自治体など、セキュリティ対策を必要とするコーポレートサイトで250社以上の実績があります。当社の運用実績を踏まえたクラウドサーバー運用のノウハウをお届けします。
コーポレートサイトをクラウドでセキュアに

サーバー管理
クロジカガイドブック
- コーポレートサイト構築・運用の課題を解決
- クロジカサーバー管理の主な機能
- 導入事例
- 導入までの流れ